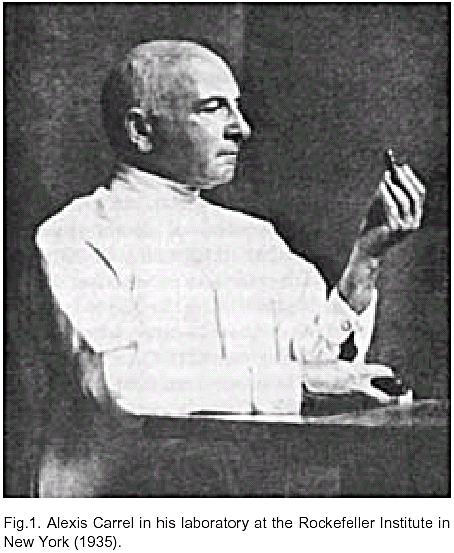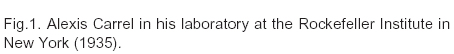第5節 奇跡を目撃した、ノーベル医学賞のカレル博士
(1/3)
|
カレル博士の略歴 |
平凡社「世界大百科事典 」『カレル.A』の項による カレル 1873‐1944 フランスの外科医。リヨンに生まれ,リヨン大学で医学を修め,1906年ニューヨークのロックフェラー医学研究所に入り,39年まで在職した。簡便な血管縫合術を開発,また組織培養法を開拓して生物学研究に新しい方法を提供した。臓器移植のため,血液や代用液を灌流させて臓器やその一部を長期間生存させる実験を続け,ニワトリ胚の心臓組織を30年余り生存させることに成功した。1912年ノーベル生理・医学賞を受賞。第1次大戦に従軍し,創傷を防腐液で灌流するカレル=デーキン法を創始して死亡率を下げた。大西洋横断飛行の C. リンドバーグと共同で35年人工心臓装置を試作した。著書《人間,この未知なるものL’homme,cet inconnu》(1935)は有名。1940年からフランスで公衆衛生調査にあたり,解放後パリで死去。 本田 一二 |
||
|
|
左の写真は、次のサイトによる。 http://www.rcjournal.com/contents/02.98/02.98.0131.asp Retrospectroscope Redux: Who Was Alexis Who?「懐旧の鏡(懐旧談):アレクシーって誰?」 この写真下の説明 を拡大した
写真1.アレクシー・カレル (1935年) ニューヨークのロックフェラー研究所の、カレルの研究室で |
||
|
左の写真(カレル博士)は、次のサイトによる。 http://www.pbs.org/wnet/redgold/innovators/bio_carrel.html
|
||
アレクシー・カレル博士は、30歳の時に、ルルド巡礼に随行した。その直後に書いたらしい手記は、和訳され「ルルドへの旅・祈り」(中村弓子訳)として、春秋社より出版されている。 アレクシー・カレル博士は、ルルドでの目撃体験を、この手記に詳細・克明に綴(つづ)っている。
|
Alexis Carrel : Le Voyage de Lourdes suivi de Fragments de Journal et de Meditations ルルドへの旅、日誌と瞑想録からの断章付き (etre suivi de qc =続いて・・・が来る 小学館仏和大辞典) Alexis Carrel : La Priere 祈り
この名著は、現在絶版中らしい。 |
||
|
1. ルルド巡礼随行の目的
|
「 −−−カレル博士がルルドへの旅をしたのは、1902年のことだった。そして博士の残した文書の中に、彼個人の話としてではないが、レラックという、本名とほとんど変わらない名前で(レラックは。カレルを逆に綴ったもの◆2)彼自身の経験を報告した物語が発見されたのである。◆1 (「ルルドへの旅・祈り」(中村弓子訳)春秋社 P.11 より) ・・・・・汽車は南仏に向かって◆3 全速力で走っていた。暑かった。空には大きな白雲が漂い、高いところからぎらぎらした光を投げかけていた。五月の午後といっても、時間が進んでくると、七月の一番うっとうしい日中くらいに、暑さは厳しかった。 (前掲書P.187)・・・・・信仰を持たないのに、カレルがあえてこの巡礼団に付き添うことを引き受けたのは、ルルドで起こるとされている奇跡の真相を科学的に調査することに、大いに興味を持っていたからだ。・・・・・ ・・・・・ルルドの奇跡と言われるものが、事実であってもペテンであっても、ともかくそれを科学的な認識の網の目にくりこむこと、そのために『ひたすら良き記録機械」に徹すること、それが当初のカレルの目的であった。 |
註◆1・・・ 「ルルドへの旅・祈り」(中村弓子訳)春秋社 P.9 より 註◆2・・・ carrel >>> lerrac 註◆3・・・HP運営者 カレル博士は、この時リヨン大学医学部外科の解剖学助手で、巡礼団の付き添い医師として、フランス南東部の都市リヨン(地中海に面したマルセーユの北260km)から汽車に乗った。 リヨンからルルドまでは、モンペリエ、ツールーズ経由で約710キロある。これは、東京−岡山間の距離と同じである。病人にとっては、たいへんな距離である。 |
|
2. 死期迫る若い娘マリー・フェラン (1) 手術を断られ、ルルドを熱望
| (「ルルドへの旅・祈り」(中村弓子訳)春秋社より P.16) 「・・・・・巡礼団の副団長格の聖職者P師は、この悪条件の汽車◆4が、哀れな病人たちに苦痛を与えているだろうと、思い遣っている様子で、実際心配していた。 『とても苦しそうな病人が二人いるのですが、モルヒネを打ってくださいませんか』とP師は、レラックに聞いた。 病人たちの積み込まれた車両は、すべて通路がなかったので、二人は一緒に次の駅で降りて三等車に乗った。◆5 車室には、八ヶ月前から重態だった娘がいた。マリー・フェランという名であった。◆6 彼女の状態はあまりに悪いので、数日前にも聖ヨゼフ病院の外科医が手術を断ったところだった。ところが、彼女はどうしてもルルドに行くことを希望したのだった。 『彼女のことは特別に頼まれて来ましたので、お世話頂けますと大変有難いのですが』と、P師はレラックに言った。そして、こう付け加えた。『彼女はあんまり弱っているので、不幸なことにならなければよいと思いますが』 (前掲書P.17)・・・車室のドアは開いていたが、座席の上に水平に広げられたマットレスのために、そちらへ入ることは出来なかった。紫色の唇で、血の気のない引きつった顔をした娘が寝ていた。 『とても苦しいんです』と彼女は言った。『でも来られてとても嬉しいんです。修道女(シスター)たちは、思いとどまらせようとしましたけど』 『今夜また見に来ますよ』と、レラックは言った。『それにもし苦しかったら、看護婦さんが私を呼びに来てくれますからね。その時はモルヒネの注射を打ちましょう』 『あなたの病人は、どうも芳(かんば)しくありませんね』と、レラックはP師に言った。 |
註◆4・・・HP運営者 この汽車には、一等客室から三等客室までの区分があった。三等客室の座席は、随分狭かっただろう。 前掲書P.13には「汽車は小さな駅に停まった。暑さがつのり、ハエがぶんぶんいっていた」とある。 この汽車は、各駅停車の「鈍行」だったのだろう。現在はルルド駅まで直通のフランス国鉄が誇る新幹線TGVがあり、快適な旅が楽しめる。 註◆5・・・HP運営者 通路は、重病人の簡易ベッドで塞がれていたのだろう、と想像する。 註◆6・・・ 本名は、マリー・バイイー(前掲書P.43) 正確な年齢は分からないが、十八歳以上は確かで、二十歳前後だったろう。 彼女の病名は、結核性腹膜炎であり、その末期と診断されている。
|
|